産休に入ったあと気になるのが出産費用やその後の生活費。産休に入ったあとは給付金が支給されます。その給付金がいつどこから振り込まれるか知っていますか?
私自身産休に入ったらお給料は出ないけど何かの制度で給付金がもらえるらしい…その程度の認識で何の手続きをいつすればいいのか分からないまま産休に入りました。
この記事では産休中にもらえる給付金について私自身調べていて分かりにくいと感じた部分を簡潔にまとめてみました。
最後は私が給付金を申請した日から振込みされるまでにかかった期間を掲載します。
給付金のスムーズな受取ができるように参考にして下さい。
産休中の給付金の種類

産休中と一口に言っても給付金に関しては一本化されておらず、産前と産後に分けて給付する目的別に申請方法や受取方法が異なります。
【産前】産休に入って出産するまでの休業期間
出産日の6週間前(42日前)多胎児の場合14週間前(98日前)
【産後】出産後8週間(56日間)の休業期間
この2つを合わせて産前産後休業(産休)と呼びますこの産休期間中にもらえる給付金は出産育児一時金と出産手当金の2種類があります。
出産育児一時金とは

出産育児一時金は、勤務先の健康保険に加入している人(被保険者)、または加入している人の扶養者(被扶養者)が出産したときに支給される一時金です。
支給されるお金
産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産の場合(妊娠週数22週以降の出産)、出産育児一時金の支給は1児につき50万円です。(2023年4月1日から)
産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産、または産科医療保障制度に加入している分娩機関での妊娠週数22週未満の出産の出産育児一時金の支給は1児につき48.8万円です。
出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため受取方法を確認しておきましょう。
*産科医療保障制度に加入している分娩期間は、産科医療保障制度のWEBサイト、または分娩機関の院内に制度のシンボルマークが表示されています。
受取方法
受取方法は3通りです。
まずは出産費用の窓口での支払を軽減できる方法として、直接支払制度と受取代理制度の2つがあります。
直接支払制度
分娩機関が保険者(健康保険組合)に直接出産育児一時金の支給申請・受取を被保険者(本人)に代わり行ってくれる制度です。
この制度を利用すると出産費用の支払いが出産費から出産育児一時金を差し引いた金額になるので、窓口で支払うときの経済的負担が軽減できます。
この制度は出産予定の分娩機関で合意文書を取り交わすだけでいいので手続きも簡単です。
恐らく出産予定の分娩機関へ健診に行ったときに案内があるはずですが、案内がない場合は窓口で直接支払制度の利用をすることを伝えましょう。
※直接支払制度を利用しない場合も合意文書が必要になります。出産費用が出産育児一時金より少ない場合、差額分が被保険者(本人)に支給されます。この場合の申請方法は加入している健康保険組合により異なりますが、出産後3ヶ月程で指定口座へ自動振込みされる場合や、自分で別途申請が必要になる場合があるので、申請に必要な書類を自分が加入している健康保険組合のHP等で確認しておきましょう。
受取代理制度
こちらの制度も出産費用の窓口での支払負担を軽減してくれるものです。
直接支払制度を利用していない分娩機関が、厚生労働省に受取代理制度の届け出をしている場合、この制度を利用できます。
受取代理制度を利用する場合は、出産予定日まで2ヶ月以内になってから、被保険者(本人)が請求手続きをするようになります。
この2つの違いは直接支払制度は分娩施設が請求手続きをしてくれるのに対し、受取代理制度は被保険者(本人)が請求手続きをすることです。
自分の出産予定の分娩施設がどちらの制度にあてはまるかによって手続き方法が変わります。
上記の制度を利用せず出産費用を窓口で全額負担した場合
直接支払制度も受取代理制度も利用しなかった場合は、出産後に自分が加入している健康保険組合に給付金の申請を行います。
その際には、必要書類を添付する必要があります。
分娩機関と直接支払制度や受取代理制度を締結していないとする合意文書の写しや、出産費用の領収書等の他、医師・助産師、区市町村長の証明などが必要となります。
健康保険組合によって必要書類が異なり、専用書式が組合のHPからダウンロードからできる場合もあります。
窓口で全額支払った場合は自分が加入している健康保険組合に確認し手続きを進めましょう。
直接支払制度や受取代理制度に比べ申請や補助金を受け取るまでの時間がかかってしまうので、出産前に自分にあった受取方法を選びましょう。
出産育児一時金の受取方法は以上です。
出産手当金とは

出産手当金とは、勤務先の健康保険に加入している人(被保険者)が出産のために仕事を休んでいた産前・産後の期間、給料がもらえなかったときに自分が加入している健康保険から出産手当金が支給されます。
*【産前】出産の日(出産が予定日より遅くなった場合は出産予定日)以前の42日(多胎児の場合98日)
【産後】出産翌日以後56日
*出産日は産前の期間に含まれます。
支給されるお金
支給日開始以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30×2/3
受取方法
出産手当金の申請書は加入している健康保険組合のホームページからダウンロードできます。
不明な場合は勤務先の担当者に確認しましょう。
出産手当金申請書は、本人が記入する欄と事業主が記入する欄、そして医師や助産師の方に記入してもらう欄があります。
産前期間分と産後期間分と分けて申請することもできますが、事業主の証明や医師、助産師の証明が毎回必要になる場合があるので、自分が加入している健康保険組合のホームページなどで確認が必要です。
私は産後期間終了後に申請しました。
後悔したのは、出産手当金の申請方法を知らなかったため、出産手当金の申請欄に記入してもらう医師からの証明をもらうために、赤ちゃんを連れて病院に行かなくてはいけなかったのが辛かったです。
病院に証明を依頼してから発行まで約2週間ほどかかりました。
出産のために入院したときにこの受取方法を知っていて出産後に記入してもらえたら、再度病院に行く手間が省けて良かったと思います。
出産育児一時金と出産手当金の違い
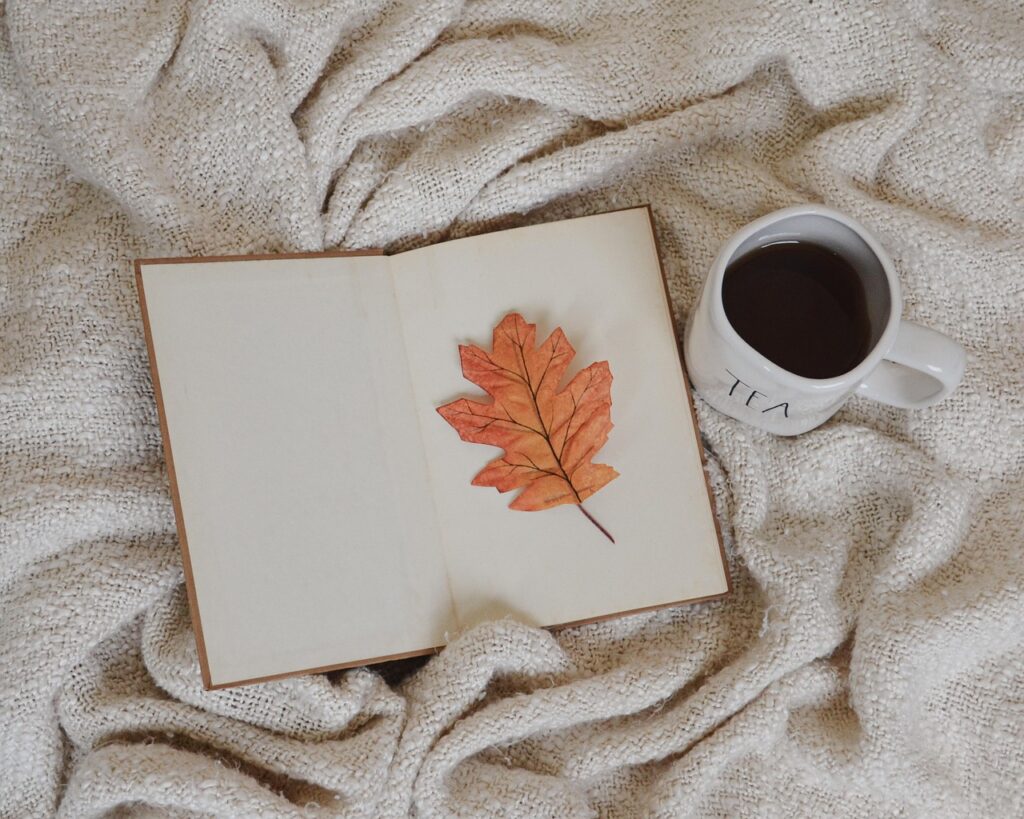
給付目的の違い
【出産育児一時金】
出産費用に関わる経済的負担を軽減させるための制度。
【出産手当金】
出産のために会社を休み給料をもらえないときに支払われる給付金。
対象者の違い
出産育児一時金は健康保険に加入している被保険者(本人)または加入している人の扶養者(配偶者等)が受け取れるのに対し、出産手当金は被保険者(本人)働きながらママになる人のみに支給されます。
給付金を実際に申請してみて入金されるまでにかかった期間
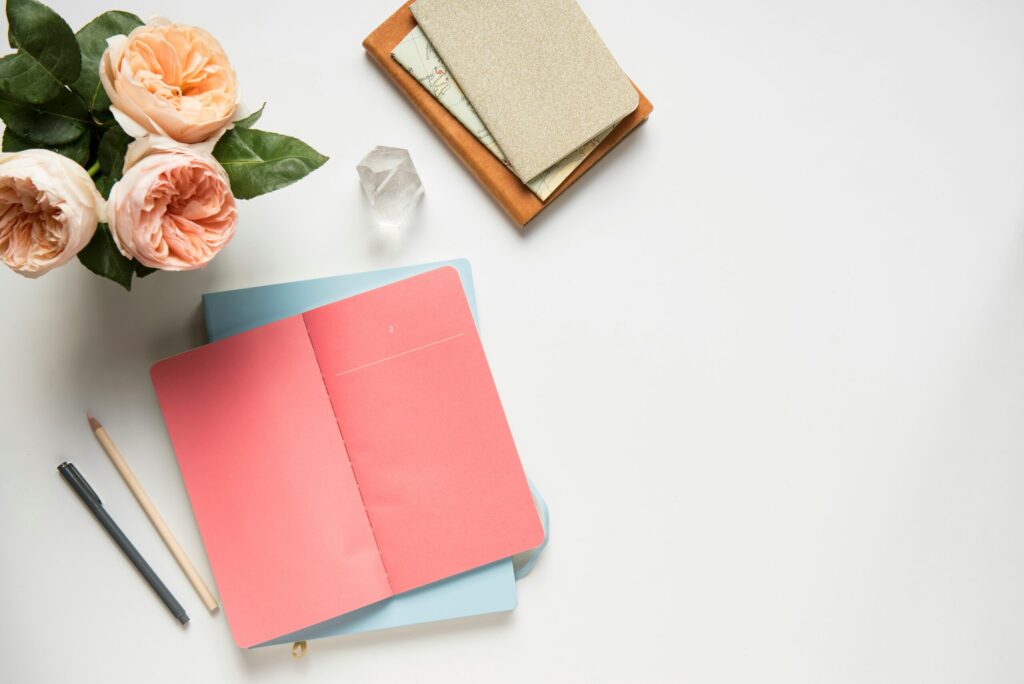
私が給付金を実際に申請してみて入金されるまでの期間を紹介します。目安として参考にしてみてください。
【参考】出産育児一時金申請後の受取までの期間
出産育児一時金の受取は直接支払制度を利用しました。そのため出産後退院時の出産費用の支払いは0円でした。
退院時に出産育児一時金での支払いができたので受取期間は0日とします。
【参考】出産育児一時金差額申請後の受取までの期間
出産費用より出産育児一時金の給付金額が多かったため健康保険組合のホームページから申請書式をダウンロードして差額申請をしました。
私の場合出産育児一時金の差額申請を郵送したのが2月7日、振込があったのは翌月の3月29日でした。
【参考】出産手当金申請後の受取までの期間
出産手当金の申請は勤務先から案内がありました。既に自分で健康保険組合のホームページから申請書式をダウンロードして分娩機関から出産の証明をもらっていたので、ここはロスタイムが少なく書類の申請ができました。
分娩機関からの証明は書類提出から自宅に郵送してもらうまで約2週間ほどかかりました。
出産手当金は勤務先の証明も必要になるため、申請書類は勤務先へ提出しました。
私の場合申請書類を4月8日に提出、出産手当金の振込があったのは翌月の5月24日でした。
出産育児一時金の差額金も出産手当金も申請から受取まで約2ヶ月弱でした。
産休の給付金のあとは育休の給付金があります!
産休中に受取れる給付金には出産育児一時金と出産手当金の2種類がありました。
加入している健康保険組合により申請方法や受取までにかかる期間は異なります。
給付金の受取がスムーズにできるように申請方法や受取方法を確認して準備をしましょう。
また産前産後休業(産休)が終わり、育児休業期間に入ると育児休業給付金が雇用保険から支払われます。
育児休業給付金については別の記事にて説明します。



コメント