妊娠が分かり喜びを感じつつも働きながら産休を迎えるまで、何から初めたら良いのか分からないことだらけで何かと不安になりますよね。出産は人生で幾度とない特別なものだからこそ、なるべく余計な心配をせずに過ごしたいですね。
この記事では妊娠が分かり産休に入るまでにやっておいて良かったこと、後悔したことを分かりやすく解説していきます。
早めにして良かった妊娠報告
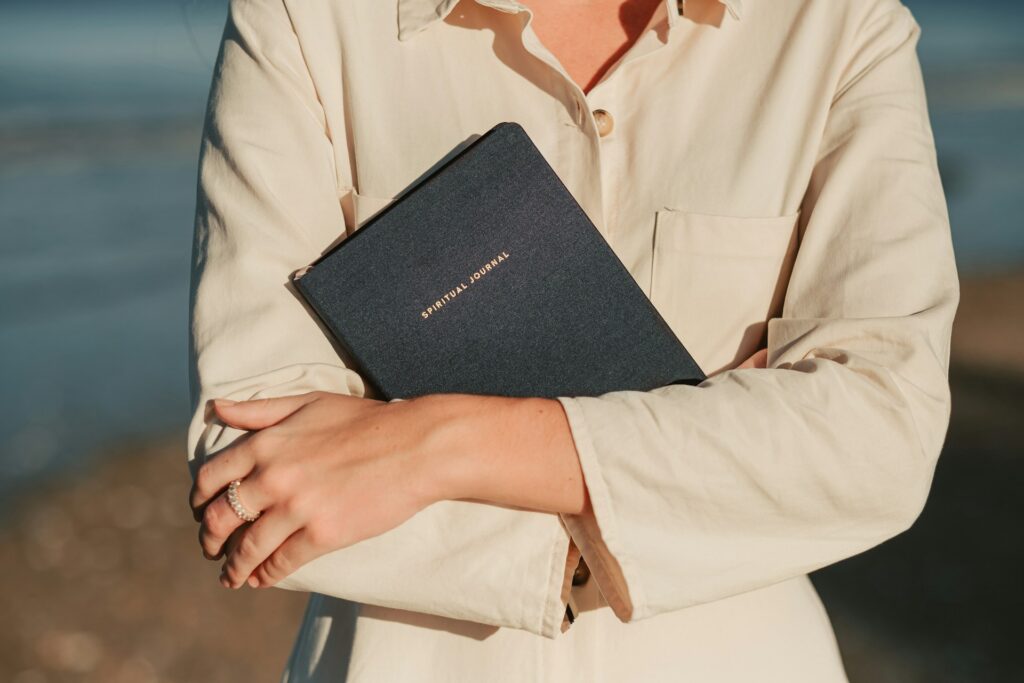
出産を迎えるまでに体は大きく変化していきます。個人差はありますが妊娠5週目頃から悪阻や体調不良等により、会社を休まざるを得ない状況が続くことも考えられます。妊娠が分かったら直属の上司だけにでも早めに伝えておけば、お休みをもらう時も安心です。
その時に、出産予定日と産休を取得して仕事復帰する意思があることも伝えておきましょう。
産休は正確には『産前産後休業』と言い、本人からの申し出により休業を取得できる制度です。この制度を利用することにより、休業期間中も給料の代わりに給付金が支給され、安心して出産を迎えることができます。
同僚への報告は安定期(妊娠16週目頃)に入ってからの報告で問題ありません。周囲に認知してもらう事で働きやすい職場環境を確保しましょう。
妊娠が分かり産休に入るまでは意外にあっという間です。産休は単胎児の場合は出産予定日の6週間前(妊娠34週目/妊娠9ヶ月)、多胎児の場合は出産予定の14週間前(妊娠26週目/妊娠7ヶ月)から始まりますが、体調等により早めにお休みに入る場合も考えられます。人手不足が嘆かれる昨今、自分が産休に入ったあとの人事配置など会社にも準備が必要です。
妊娠が分かったら会社に報告しましょう。
マタニティウェアはお仕事服もマタニティ用に

妊娠中期(妊娠16週目)に入りこの頃になるとお腹のふくらみを感じ始める頃です。お腹のふくらみがまだまだ分からない場合でも、戌の日を過ぎたらお腹周りを締め付けないマタニティウェアに移行していきましょう。普段来ている服とマタニティウェアの違いは身体への締め付けがないことで圧迫から赤ちゃんを守り、これから変化していく体型に対応ができるように設計されています。
妊婦さんは身体を冷やさないようにと昔から言われていますが、そもそも妊娠中はホルモンの変化で体温調整が上手く出来なくなり、身体が冷えやすくなっているので、保温性に優れたマタニティウェアや冷え対策グッズを使用することで、冷えからくる倦怠感や、お腹の張りなど、母体にもたらす影響のほか、血液の流れが悪くなることで、赤ちゃんの発育への悪影響を回避できる可能性が高まります。
妊娠初期でも悪阻が辛い場合や、お腹の締め付けが気になる場合は、快適に過ごせるように早めにマタニティウェアに移行すると良いでしょう。
お仕事用のマタニティウェアも手頃なお値段で機能性に優れた、かわいいデザインのものが数多く販売されています。マタニティウェアならではの、やわらかくて、優しいデザインがお仕事を続けながら赤ちゃんを身ごもるママを包み込んでくれます。
マタニティ服を着た働くママを見かけると優しい気持ちになりますよね。妊娠中期に入ったら、マタニティウェアに着替えましょう。
受けて良かった歯科健診

体調が落ち着いてくる時期である、妊娠中期に歯科健診を受けておくのがおすすめです。働いていると、歯医者に通うことが難しいと感じ痛みがなければ、ついつい後回しになりがちですが、妊娠中は虫歯や歯周病になりやすいと言われています。自治体によっては無料で歯科健診を受けられる場合もあるので是非確認してみましょう。
とは言え妊娠中の治療は応急処置にとどまり治療ができない場合もありますが、歯の大切さを再認識できる機会でもあり、生まれてくる赤ちゃんの歯を健康に守ってあげようと思える良い機会になります。
妊娠中期に入ったら歯科健診に行ってみましょう。
準備して良かった業務の引継ぎ資料
産休に入ると1年超の間不在になります。体調と相談しながら早めに引継ぎ資料の準備しましょう。
自分の業務を洗いだし、日々やること、月次で行うこと、不定期で発生することなど、まずは書き出してみましょう。あなただったらすぐに分かることも、同僚や、新人さんの場合、業務が停滞してしまう事も考えられます。
引継ぎの資料はWordやExcelの他、自分が作成しやすい書式で問題ありません。
どうやって作ったらいいか困ったときは、インターネットで引継ぎ資料を作成できる無料のテンプレートがあるので、そちらを試してみると良いかもしれません。
簡単なものでも、業務の流れや手順は分かりやすい資料を作成しておきましょう。引継ぎを任せられた人も安心です。またしっかりと引継ぎをしてくれたと、あなた自身への信頼にも繋がるはずです。
確認しておけば良かった産休育休に伴う手続き
産休に伴う手続きは色々ありますが、法律に定められた産休や育休には、社会保険料の免除や、給付金に伴う手続きが必要です。
その多くは会社が行ってくれる場合が多いですが、中には従業員が申請できるものもあるので、トラブル防止のため心配な場合は事前に確認しておきましょう。
手続きに必要なものを事前に知っておけば余計な手間が少なくなり、給付金申請までの時間も短縮できます。
産休や育休には制度により何かと恩恵を受けられる事が多いですが、住民税に関しては産休、育休中の免税の対象になりません。
住民税は前年の1月~12月に一定の所得があった人が課税対象となり、その分を6月から翌年5月にかけて納税しています。
そのため産休や育休に入っても、前年度分の所得に対しての住民税の支払いが発生します。
通常、会社で働く人は住民税が給料から天引き(特別徴収)されていますが、産休に入ると会社からの給料の支払いがないため(普通徴収)され自分で納付することになります。
1月~5月までに休業に入る場合は5月までの住民税を最後の給料から天引き(一括徴収)されます。6月~は前年の所得に対し住民税が普通徴収に切り変わり自分で納付します。
普通徴収は管轄の自治体から住民税の納税通知書が郵送されてきます。年税額で通知書と納付書が届くので一括、または4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて、コンビニ払いや金融機関振込みなど指定の方法の中から選び支払います。
毎月天引きされていた住民税を、まとめて支払うように変わるので1回の支払いが高額になります。給料の振り込みがなくなり、赤ちゃんを迎える準備で出費が増えるなか負担を感じやすくなりますが、滞納したり未納のままでいるとペナルティが科せられます。
支払いが難しいときは自治体の窓口で早めに相談しましょう。納税が困難と認められる場合、育休中の最長1年間は住民税の支払猶予を受けられることがあります。あくまで支払の猶予であり、免除ではありませんが、放置すると良いことはないので納税が困難な場合は早めに相談しましょう。

